赤頭巾ちゃんの時代背景
本日は、「赤頭巾ちゃんのロマンス 第4場」 http://stanislavskii.tabigeinin.com/romance.htm のレッスンを行いました。

皆さん、すごく良かったですよ、文句なしです。上手になりましたね、本当にうれしいです。
◇ ◇ ◇
どちらかというと・・・演技よりも当時の社会情勢について、いろいろ説明しながらレッスンを進めました。

それはだいたい、こんな内容です。
フランスでおとぎ話が大人たちの間で語り継がれ、全盛を極めたのは17世紀後半のこと。
当時の「おとな」の定義は、男性では13歳で王位についた例もあり、女性は12歳で結婚適齢期。結婚することもまれではなかった。
17世紀の貴族にとって結婚とは、社会的地位や経済的利益のために親が取り決める商談であり、資産の交換にすぎないのだ。
つまり政略結婚。
フィリップ・アリエスらの歴史家によれば、幼児期や思春期が今のように長くなったのは、人類の歴史の中でもほんの最近のことだという。
数百年前までは、子どもは幼いうちに死んでしまっていた。
そして延命できると判断されるや、ただちに成人として扱われることとなり、非常に早婚だったのも、若いうちに命を落として政略結婚ができなくなるのを警戒したからで、
中産階級や下層階級の子どもたちは産着を脱ぐと、そのまま仕事場に送り込まれ、11、12歳で成人扱いされていた。
1556年の勅令では、たとえ愛し合う仲でも、親の了解なしに隠れて同棲すること、つまり「人目を忍んで」の結婚は非合法とされた。
1673年の法令は、25歳まで、あるいは結婚するまで、娘を幽閉しておく権利を父親に与えていた。
19世紀の中流農家の若い女性は社会から隔絶され、ひたすら結婚を待ちながら生きてきた。
教育は最低限にとどめて、料理・家事と花嫁修業に徹し、
また裕福な家庭の娘にしても、寄宿学校に入るのが普通で、そこそこの学費でそこそこの教育を受け、卒業しても天才と呼ばれるような危険はないように育てられた。
参考文献
「赤ずきんちゃんはなぜ狼と寝たのか」河出書房新社
◇ ◇ ◇
「グリム童話メルヘンの深層」 のなかで、著者の鈴木晶氏は、こう書いているわ。

ヴィルヘルム・グリムが「女は黙っておとなしくしているべきだ」と考えていたことは明らかだ。それが証拠に、童話集の中には、女が沈黙を強いられる話がいくつもある。

それがホントだとしたら、グリムにはちょっとガッカリですね。

「グリムが」というより、そういう時代だったんでしょうね。女性の権利が認められるようになったのは、つい最近だもの。
グリム童話ではないけれど、「アリ―テ姫の冒険」という童話があるわ。

アリーテ姫は、宝石に目がない父親の王と2人で暮らしているの。
彼女は、メルヘンの主人公たちとは違って、「美しい」とは形容されず、「賢い」と形容されてるわ。本を読むのが大好きで15歳のころには、王様の書斎にある本をぜんぶ読み終えてしまったくらいなのね。
アリーテ姫と従来のメルヘンの主人公との最大の違いは、彼女が自分の頭で考える能力をそなえ、はっきりと自分の意見を主張すること。

なんか好感が持てますね。
アリーテ姫は、乗馬やダンスのレッスンは大好きだけど、話し方のレッスンは大嫌い。

なぜなら話し方の家庭教師が、「まあ、ほんとうでございますか」「なんて興味深いお話なんでしょう。もっとお聞かせください」といった話し方ばかり教え込もうとするから。
彼女はいつでも「私はこう思います」とか「私の考えでは」と言ってしまうのね。
娘が「賢い」ことを知った王は仰天し、「もし、賢いなんていうことが世間に知れたら、おまえは一生、結婚できない」
「賢い妻を求める男など、この世にいるわけがない。女はやさしく、かわいいのがいいんだ」と言い、アリーテ姫が賢いということが世間に知れる前に、結婚させてしまおうと考えるの。

かなり時代を感じさせられますね。娘のためを思って言ってるんだろうけど・・・そこまでいくとちょっと。

そう。
「そんな気持ちをお芝居に反映させよう!」とアドバイスしたの。みんな、すっごくいい演技をしてくれた。とっても面白かったよ。
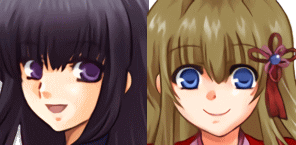
時代背景を知ることで、演技やセリフに深みが生まれるよ。
それでは、また来週!
参考文献
「グリム童話メルヘンの深層」 講談社現代新書
◇ ◇ ◇

【新入生募集中!】
18歳以上
年齢制限・入所試験なし。
無料体験入学 & レッスン見学受付中!
Voice actor laboratory 声優演技研究所
